

私たちの暮らしには、米と同じくらいパンや麺が重要です。もともと米を中心に食べてきた私たち日本人にとって、小麦は米と同様に重要な作物と言えます。ですが、米とは異なり小麦はそのまま食べる事はありませんし、国内産か海外産といった区別も、小麦粉や、ましてやパンや麺などの製品からは区別がつきません。
私たちは顔の見える生産者として、国産小麦のブランドや安全性に責任を持ち、食べてくれた人が「安全で美味しい」と喜んでもらえることに情熱を注いでいます。日々、小麦の一粒一粒のおいしさを考えた品種を妥協することなく育てています。
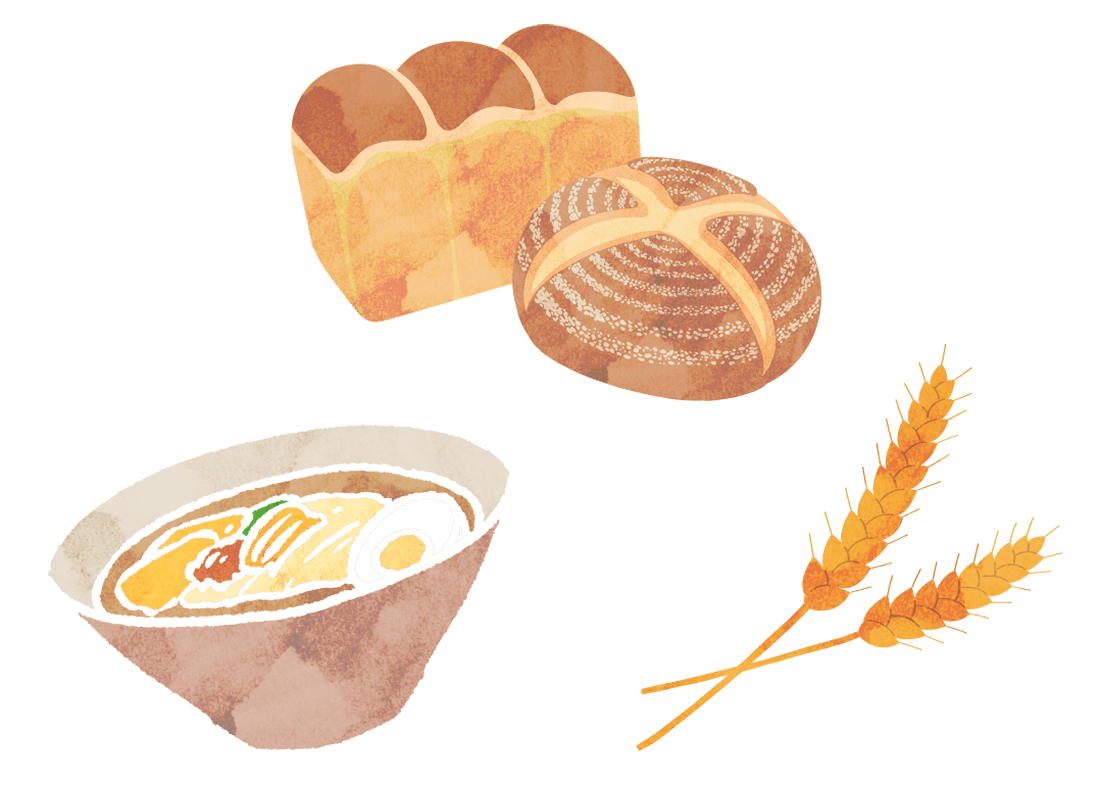
秋まき小麦とは、秋に種をまいて翌年の春から夏にかけて収穫する小麦のことです。秋に種をまくことで冬の間にじっくりと成長し、春以降に一気に生育が進みます。寒さに強い品種が多く冬の低温にさらされることでしっかりとした実をつけます。優しい風味が特徴で、お菓子やうどんなどに多く使われています。


「きたのかおり」はグルテン量が多く、主にパンに適した強力系の品種です。もっちりとした食感と豊かな風味が特徴で、焼き上がりの色が濃く、独特の香ばしさがあることから、個性を大切にするパン職人から人気のある品種です。すばるでも原種を維持し、人気のパン職人さんからのオーダーを受けて、こだわりを持って生産しています。

「ゆめちから」は超強力小麦の品種で、特にパン作りに適しています。たんぱく質含量が高く、グルテンの力が強いため、外国産の強力粉に匹敵する製パン性を持っているため、モチモチとした食感や豊かな風味が味わえる、国産小麦100%のパン作りを可能にします。また、他の国産小麦とブレンドすることで、多彩なパンをつくることができ、パン職人や製粉メーカーさんからも高く評価されています。

「つるきち」は、北海道産の希少な小麦品種で、「まぼろしの品種」とも称される特別な存在です。1970年代に開発され一度は市場から姿を消しましたが、その独特の風味やモチモチとした食感が評価は高く評価されており、私たちは原原種を維持しながら、生産を続けています。希少で生産量も限られるため、入手が難しい品種ですが、私たちの仲間のお店で食べてもらうことができます。
春まき小麦とは、春に種をまいて同じ年の夏に収穫する小麦のことです。翌年ではなくその年のうちに収穫できるのが特徴です。北海道の涼しい春から夏の期間は、春まき小麦の成長に適していて、小麦がストレスなく育ちます。小麦の風味が豊かで強くパンなどに多く使われています。


「はるよこい」は、北海道で生産される強力小麦の品種で、主にパン用として人気があります。焼き上がりの色がややクリーミーで、小麦の風味がしっかり感じられるため、風味豊かなパン作りに適しています。寒冷地でも安定して収穫できることから、北海道産小麦の代表的な品種の一つとなりました。
「原種、原原種をつくる」という取り組みは、品種改良の前の状態や種の安定供給を守るために、基本となる種を育成することです。例えば、「原種」は新しい品種を作るための元となる種で、これを使ってより良い作物が生みだされていきます。そして、「原原種」はそのさらに前の段階の種で、最も純粋な状態の種です。
抜き取りと言う異形穂などを抜き取る作業など、大変なことも多いです。でも原種をつくり守ることによって、将来にわたって安定して品種を供給でき、地域の農業を支える大切な役割があります。


例えば「つるきち」と「キタノカオリ」については、種の供給が難しくなっています。ですがこれらの品種を使って、とても美味しいパンや麺を製造されている方達がいます。そしてその美味しさを楽しみにしている消費者の皆さんがいるのです。
私たちは、「つるきち」はタネになる前々の原原種から、「キタノカオリ」はタネの前の原種から生産し、直にタネの供給をしています。これらの品種を守り続けることは、地域の農業や食の未来にもつながる重要な取り組みだと考えています。
「原種、原原種をつくる」という取り組みは、品種改良の前の状態や種の安定供給を守るために、基本となる種を育成することです。例えば、「原種」は新しい品種を作るための元となる種で、これを使ってより良い作物が生みだされていきます。そして、「原原種」はそのさらに前の段階の種で、最も純粋な状態の種です。
抜き取りと言う異形穂などを抜き取る作業など、大変なことも多いです。でも原種をつくり守ることによって、将来にわたって安定して品種を供給でき、地域の農業を支える大切な役割があります。

近年、天候の変化に伴い、栽培方法も多くの工夫と勉強を重ねながら進化しています。私たちは、作物の状態を見守りながら、適切な防除や圃場管理を行うことで、品質の良い小麦が育つように尽力しています。変化に柔軟に対応し、より良い作物を育てるために日々努力を怠りません。

大切なこと.01
一番大切なことは、作物の生育状態をよく「見る」ことです。土の状態、天候による変化、作物の成長具合、害虫や病気の兆候など、よく見て今までの経験と照らし合わせて、細かな問題に早期に気づくことがとても大切です。そのためには日々の観察を怠らず、変化に柔軟に対応することが求められます。
大切なこと.02
土壌診断をしっかり行い、ミネラルバランスを把握し適正化することが重要です。特に、窒素・リン酸・カリに加え、カルシウムやマグネシウムなど微量要素の調整が生育に影響を与えます。また、微生物を活性化させることで、土壌の養分循環を促して健全な成長を支えます。こうした管理により生きた土を維持し、持続的で健康な小麦栽培が可能になります。
大切なこと.03
小麦の健全な生育には、適切な水管理が不可欠です。特に過剰な水分は根腐れや病害の原因となるため、暗渠排水(地下排水設備)を整備して、圃場の排水性を維持することが重要です。これにより余分な水を排出し、根が酸素を十分に吸収できる環境を維持できます。また、微生物の働きを促進することで柔らかい土作りをし、水はけと保水のバランスを整えて安定した環境で小麦を生産します。
大切なこと.04
小麦の病害虫対策には、頻繁な圃場観察が重要です。作物の生育状態をこまめに確認し、湿度・温度の経過を把握することで、病害発生の兆候を早めに察知できます。特に、害虫が発生しやすい環境を未然に防ぐため、排水管理を徹底し、湿度を調整します。また、場合によっては適切な農薬の予防散布を行い、発生前の対策を徹底することで、被害を最小限に抑え、品質と安全性を両立した健康な小麦を育てることができます。
大切なこと.05
天気予報、天候予測の機能を活用し、適切な農作業計画を立ています。複数の天気アプリを活用して降雨や気温の変動を詳細に比較分析することで、精度の高い予測をします。また、気象ロボットを導入し、圃場の温度・湿度・風速データをリアルタイムで収集することで、より正確な気象判断ができます。天候リスクを最小限に抑えた安定した小麦生産が可能になります。
大切なこと.06
小麦の収穫タイミングは極めてシビアな見極めが求められ、1日でも誤ると品質や収量に大きく影響してしまいます。穂の成熟度、水分含量、気象条件を総合的に判断し、最適なタイミングを見極めることが重要ですが、特に、収穫日付近の気候や朝露の影響、湿度の変化、夕立の可能性まで細かく確認し、適切な日時に作業を進める必要があります。勘と経験だけでなく、最新の気象データや収穫機器の活用により、精度の高い収穫判断になるよう研究しています。
Contact Us